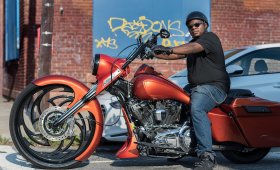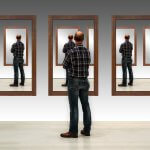ブロックエディタを解除する。クラシックエディタがいい
 Image by Jill Wellington from Pixabay
Image by Jill Wellington from Pixabay
2022.08.29(更新日:2022.08.29)
ver5.0からメインエディタとして使われ初めた「ブロックエディタ」。
バージョンごとに改良されているようなのだが、すべてのサイト編集にピッタリ!・・・と言う訳にはいかない。
なので旧エディタ「クラシックエディタ」に戻す方法を、すっかり忘れてたので記事にする。
この記事は1年以上経過しています。内容的に古い場合があります。
プラグインを使う
Classic Editor
公式のプラグイン。インストール、有効化するとクラシックエディタに変更出来る。ブロックエディタと旧エディタの切り替えも出来るように設定出来る。
ただし公式ページには
「Classic Editor は公式な WordPress プラグインであり、少なくとも2022年まで、または必要なくなるまでの間、完全にサポート・保守されます」
公式ページより引用
とあるので注意が必要。頃合いを見て他に変更する必要があるかも。
Classic Editor Addon
こちらも公式プラグイン。Classic Editorを導入する際はいっしょにインストールした方が良いだろう。これはClassic Editorのみでは削除出来ないブロックエディタに関するラベルやリンクなど不要なものを削除してくれるようだ。
Disable Gutenberg
こちらも公式プラグイン。こちらもClassic Editorと同じ機能を持ちながら、さらに細かい設定が出来る。
Classic Editorを使ってもソースコード内に現れる「global-styles-inline-css」も消してくれるみたい。
一番の大きな違いはClassic Editorのサポート・保守の期限があるのに対し、こちらは継続的な開発を予定されているとのことなので(神!)今後インストールするならば、こちらを使用した方が良いかもしれない。
プラグインを使わない
functions.phpに書き込む方法。シンプルかつ手っ取り早い。CSSの削除に関してはテーマに合わせて必要なものだけ使用。
/* functions.php内 */
// Gutenbergを無効
add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 10);
// 自動挿入されるGutenberg用CSSを削除
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'remove_block_library_style' );
function remove_block_library_style() {
wp_dequeue_style( 'wp-block-library' );
wp_dequeue_style( 'wp-block-library-theme' );
}
// global-styles-inline-cssを無効化する
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'remove_global_styles' );
function remove_global_styles(){
wp_dequeue_style( 'global-styles' );
}
おまけ・CMSとしてのWordpressにおけるブロックエディタを考える
運営者が好みに合わせてレイアウトを自由に変更出来るように、コードを意識しないで変更できると言う代物がブロックエディタ。
ただ顧客に「CMSとして導入してもらっているサイト」の場合、少々難があると個人的には考える。
なぜならレイアウトを含めたページのデザインに関し、すでに希望の通り作成したものを納品すると言う立場において、好き勝手に編集することを「お好きにどうぞ!」とはなかなか言いづらい。テイストも変わるかもしれないし、CSSだって追加した部分が反映する保証はないからだ。
いろいろ編集された挙げ句に「直して〜」となるのは、なるべく避けたいのが本音なのである。
自由にレイアウトが出来ると言うデメリット
あくまで「自分の好みに絶対したい」かつ「自分で作成してみたい」人はいいと思うが、ブロックエディタを使用すると言うことは「レイアウトまで考える」ことになる。
納品時にサイトは少なくともトータルデザインでまとめているので、テキトーにすると異質なページが出来上がる場合もある。かつレスポンシブで作成したサイトの場合、その辺を考慮しないレイアウトは・・・想像も出来ない。
学習のコスト
大抵の場合「多機能 = 操作いっぱい」が当てはまると思う。
もちろんブロックエディタは考えられた操作性の上に出来ているので、慣れてくれば格段に使いやすいだろう。
だたしクラシックエディタで「新規で記事作成する」ことだって四苦八苦する人もいるので、操作ボタンがいっぱいあるのをマスターするのは困難極める。
決まった部分の文字編集が出来れば良い人にとって、それ以上の学習は「面倒くさい上に不要」。
またその操作をレクチャーするのも制作側になるので、一通り教えるとなるとかなりの時間が必要となり制作側としても余計なコストがかかる。
使わないものは削除し、顧客にはその時間を顧客の実務に使用してもらう。その方が双方にとって精神的にもいい。
結論
唯一、自由度を持たせるページにするならば「お知らせ」や「ブログ」系のページだろう。
「ここはお好きにどうぞ」と遊んでもらい、操作に慣れ親しんでもらうのが良いと思う。
少なくとも自分がReactをマスターするまで(難)